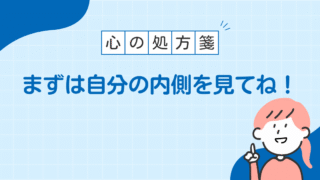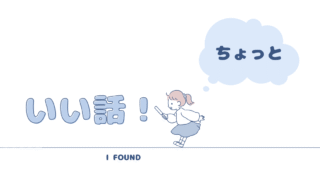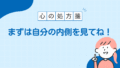今日は「マインドフルネス」について書きます。
マインドフルネスとは?
まず、マインドフルネスとは? 「今この瞬間」に意識を向けて、評価や判断をせずにありのままを受け入れる心の状態のこと。仏教の瞑想法にルーツを持ちつつ、現代ではストレス軽減や集中力向上、心の安定のための心理技法として世界中で実践されています。
世界的なIT企業や日本の大企業でも導入が進み、瞑想などとともにマインドフルネスを取り入れてビジネスの現場に生かしているようです。
マインドフルネスの歴史と提唱者
起源
- 古代仏教にルーツがあり、パーリ語の「サティ(Sati)」=気づき・記憶・注意が原点。
- 仏教の修行体系の一部として、心の安定と洞察を深めるために用いられてきた。
現代の提唱者
- ジョン・カバット・ジン博士(米マサチューセッツ大学医学部名誉教授)が1979年に「マインドフルネスストレス低減法(MBSR)」を開発、仏教瞑想やヨガの実践を医療に応用し科学的に効果を実証した。
- 他にも、ティク・ナット・ハン(ベトナム人僧侶)や鈴木大拙(仏教学者)などが世界的普及に貢献した。
基本的な考え方
- 今ここにあること:過去や未来ではなく「今この瞬間」の体験、思考や感情、感覚にフォーカスして意識を向ける。
- 評価しない:良し悪しの判断をせず、ただ「あるがまま」を観察する。
- 気づきの訓練:呼吸、身体感覚、感情、思考などに気づく力を育てる。
瞑想に通ずるところ
瞑想する際に、深い瞑想状態への移行のプロセスとして、まずは「多念多心」つまり日ごろの雑念でいっぱいの脳の状態を整理整頓して、やがて「一念一心」ひとつのことに意識を集中する状態に移行する。それが、最終的には「無念無想」の状態へと移行して深い瞑想状態に至るというアプローチがあります。
上記の移行プロセスの「一念一心」という状態が「マインドフルネス」であると私は理解しています。
常住坐臥
師・中村天風は瞑想のことを“安定打座”と称しましたが、「常住打座」と言われ、つまり「いつ如何なるときにも“安定打座”、つまり瞑想状態の心境で日常生活を送りなさいと説かれました。
また、禅にも“常住坐臥”という教えがあります。それは精神的な安定や静寂を求める生活態度や修行の姿勢を象徴する言葉で「日々の喧騒から一歩引いて、内面の平和を保つことの重要性」を説いたものです。
マインドフルネスのアプローチは、このように“安定打座”や“常住坐臥”の考え方に共通するもので、覚醒に至るひとつのカタチであると言ってもよいと思います。
代表的な実践方法
| 方法 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 呼吸瞑想 | 呼吸に意識を集中する。雑念が浮かんだら、ただやり過ごしまた呼吸に戻る | 5〜20分 |
| ボディスキャン | 頭のてっぺんから足のつま先まで、順番に身体感覚を観察する | 10〜30分 |
| 歩行瞑想 | ふだんは意識せずに行っている「歩く」という動作に意識を向けながら、歩くという体の動きを味わいながらゆっくり歩く | 5〜15分 |
| 食事瞑想 | 食べ物の味・香り・食感に集中して食べる。自然と感謝がわいてくるのを楽しみながら、静かな喜びとともにいただく | 食事時間 |
マインドフルネスの効果
- ストレスの軽減と心の安定。上述したMBSRは、慢性ストレスや不安症状の緩和に有効であることが確かめられた。
- 集中力と創造性の向上。注意力や認知機能の改善も認められた。
- 感情のセルフコントロール力アップ。怒りや不安などの感情を客観的に観察できるようになる。
- 睡眠の質の改善。リラックス効果により入眠しやすくなる。
- 自己理解と共感力の深化。自分の思考や感情により深いレベルで気づく力が育まれる。